投資で不安を解消しようとすること
危険性: 老後の経済的な不安から投資を始めようと考えるのは非常に危険であり、資産を大きく損なう要因となり得ます。漠然とした不安感から投資を行うと、業者に利用され、よく分からないままにハイリスクな運用方法にお金を投じたり、甘い言葉に載せられてぼったくり商品を買わされる可能性があります。その結果、資産があまり増えなかったり、場合によっては大きく減らしてしまい、老後生活がより苦しいものになりかねません。
投資は老後に備えるための一つの方法に過ぎず、根本的に大切なのは、年金収入や毎月の支出を考慮した自分なりの生活設計です。適切な運用には、生活設計に基づいた地に足のついた計画と知識が必要です危険性: 老後の経済的な不安から投資を始めようと考えるのは非常に危険であり、資産を大きく損なう要因となり得ます。漠然とした不安感から投資を行うと、業者に利用され、よく分からないままにハイリスクな運用方法にお金を投じたり、甘い言葉に載せられてぼったくり商品を買わされる可能性があります。その結果、資産があまり増えなかったり、場合によっては大きく減らしてしまい、老後生活がより苦しいものになりかねません。
投資は老後に備えるための一つの方法に過ぎず、根本的に大切なのは、年金収入や毎月の支出を考慮した自分なりの生活設計です。適切な運用には、生活設計に基づいた地に足のついた計画と知識が必要です。
短期で儲けようとすること
「高齢期が近いから投資期間が取れない」「今更インデックスファンドの長期運用は難しい」といった考えから、個別株やレバレッジ型の商品に投資して短期で利益を狙うのは非常に危険です。高いリターンを求めると、必然的にリスクも極めて高くなります。例えば、個別株は企業の不祥事で暴落する可能性があり、3倍レバレッジ商品は株価が10%下がると30%の損失となります。これらは安定的に老後資金を作る上では全く向かず、大きな損失を出して取り返しがつかなくなる可能性があります。
投資は、購入した銘柄やファンドを持ち続けることです。市場は予測できない変動があるものの、長期で見れば右肩上がりに成長していくことが見込まれます。厚生労働省のデータによれば、60歳時点でも平均余命は20年以上の運用期間が取れ、家族全体で見ればさらに超長期での運用も可能です。「高齢期が近いから投資期間が取れない」「今更インデックスファンドの長期運用は難しい」といった考えから、個別株やレバレッジ型の商品に投資して短期で利益を狙うのは非常に危険です。高いリターンを求めると、必然的にリスクも極めて高くなります。例えば、個別株は企業の不祥事で暴落する可能性があり、3倍レバレッジ商品は株価が10%下がると30%の損失となります。これらは安定的に老後資金を作る上では全く向かず、大きな損失を出して取り返しがつかなくなる可能性があります。
コストに無頓着であること
コストの違いは、長期的に見ると莫大な影響を及ぼします。例えば、年間手数料0.1%のファンドと2%のファンドに300万円を投資し年利4%で30年間運用した場合、最終的な手取り額に400万円以上の差が出ます。高いコストを払ったからといって、必ずしも利益が出る保証はなく、実際には大半のアクティブファンドはコストゆえにインデックスファンドより成績が劣ることが分かっています。金融機関は50代以降の世代を狙って、高コスト、つまり売り手が儲かる商品を提案する傾向があります。
毎月分配型投資信託を購入すること
60代以上の投資信託保有者の約半数が毎月分配型ファンドを持っているとされていますが、これは購入を避けるべき商品です。まず、購入時手数料が3.3%、信託報酬が年率2%近くかかるなど、高額なコストがかかります。さらに、年利20%もの高すぎる分配金利回りは、株式市場の平均利回り(5~7%程度)から見て現実的ではありません。この高い分配金は、投資元本を切り崩して支払われていることが多く、「タワし配当」とも呼ばれます。これは、業者に高額な手数料を払いながら、自分の資産を自ら取り崩しているようなもので、投資家にとって非常に不利な商品です。
今後「プラチナNISA」が創設され、毎月分配型ファンドが解禁される見通しがあり、金融機関からの積極的な提案が増える可能性があるので注意が必要です。60代以上の投資信託保有者の約半数が毎月分配型ファンドを持っているとされていますが、これは購入を避けるべき商品です。まず、購入時手数料が3.3%、信託報酬が年率2%近くかかるなど、高額なコストがかかります。さらに、年利20%もの高すぎる分配金利回りは、株式市場の平均利回り(5~7%程度)から見て現実的ではありません。この高い分配金は、投資元本を切り崩して支払われていることが多く、「タワし配当」とも呼ばれます。これは、業者に高額な手数料を払いながら、自分の資産を自ら取り崩しているようなもので、投資家にとって非常に不利な商品です。
不動産投資を安易に始めること
50代以降の方が老後対策として安易に現物の不動産投資に参入するのは避けるべきです。株式とは異なり、不動産はプロや得意先に良い物件が回されるため、初心者は収益性の低い物件を高値で掴まされる可能性が高いです。想定通りの家賃が取れず、ローン返済や管理費用が家賃収入を上回ったり、空室によって赤字が拡大するリスクがあります。今後は人口減少が急速に進むため、空室リスクはさらに高まります。また、不動産は流動性が低く換金に時間がかかり、売却したくても売れなかったり、希望価格で売れずに大きな残債が残ることもあります。不動産投資の失敗は金額が大きいため、ダメージも桁違いに大きく、家族にも多大な迷惑をかけることになりかねません。
ポートフォリオの一部として、質の良いリート(不動産投資信託)を保有することは良い選択肢です。
じゃあ、どうすればいいの?
落とし穴の回避策と推奨される投資
これらの落とし穴を回避し、堅実な資産形成を行うためには、まず自分なりの老後の生活設計を考えることが重要です。その上で、以下のような対策や投資が推奨されます。
1. 生活設計と計画を立てる
◦ 高齢期にもらえる年金などの収入、毎月の支出を明確にし、どの程度の資産が必要か把握することが不安の解消につながります。
◦ 節約スキルの習得、健康への投資による収入増、年金の繰り下げ受給の利用など、様々な対策を自分に合ったバランスで総合的に行うことが大切です。
2. 市場全体に投資する低コストのインデックスファンドを活用する
◦ 推奨商品: S&P500などの米国株、オルカンなどの全世界株、先進国株式など、市場全体に分散投資できる商品が推奨されます。
◦ 選び方: 購入時手数料が無料、信託報酬が年間0.2%以下のものを選びましょう。
◦ 運用方法: 新NISAを使ってリスク許容度の範囲内で購入し、基本的には持ち続けることが重要です。お金が必要になった際は、必要な分だけをその都度売却して現金化します。
◦ 老後収入の確保: 毎月分配型ファンドではなく、証券会社の定率または定額売却サービスを利用することで、効率的に一定額の資産収入を得ることができます。
◦ シミュレーション: 例えば、50歳の方が65歳までの15年間、毎月10万円を全世界株に投資し年利5%のリターンを得られた場合、65歳時点で資産は2673万円になります。この資産を年利5%で運用しながら月12万円ずつ取り崩すと、113歳まで持つ計算になります。
3. リスクを抑えたい資金には「個人向け国債 変動10年」を検討する
◦ 推奨商品: 日本政府が発行する10年満期タイプの国債で、元本保証があり、普通預金に比べて利回りが高いです。
◦ 利点: 今後インフレで金利が上昇した場合には利息も上昇するため、物価上昇にもある程度対応できます。購入から1年経過すれば中途換金も可能です。国が発行しているため、民間の銀行預金に比べて安全性が高いと言えます。
まとめると、生活防衛資金などの一定の現金は銀行預金で持ちつつ、リスクを取ってもいいお金は低コストのインデックスファンドを、リスクを取らずに運用したいお金があれば個人向け国債 変動10年を保有する、というシンプルなポートフォリオが多くの人にとって最適な選択肢となります。
50代・60代での投資の失敗は致命傷になり得るため、老後への不安感から安易な投資に手を出したり、不労所得などの甘い言葉に惑わされたりせず、堅実な資産形成を心がけることが大切です。
出典先動画
【絶対やるな】老後資金が溶ける。50代・60代の投資失敗パターン5選

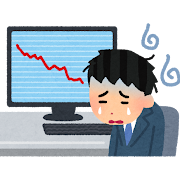
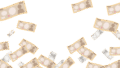

コメント